
住宅ローンを検討する際、多くの方が「変動金利」と「固定金利」のいずれを選ぶべきかで迷われます。
今後金利が下がると予想される局面では変動金利を、金利上昇が見込まれる局面では固定金利を選ぶのが理想とは言われています。
しかしながら、将来の金利動向を正確に予測することは困難であり、「どちらを選ぶべきか」と悩む方は非常に多いものです。
そこで本記事では、住宅ローンの金利がどのように決定されているのか、その仕組みを解説します。
特に、「短期プライムレート(短プラ)」および「長期プライムレート(長プラ)」という2つの金利指標が、金利設定にどのように関わっているのか、その仕組みや違いを取り上げます。
金利の仕組みや違いなどを知っておくことで、ご自身に合った住宅ローンを選ぶ手がかりになるはずです。
目次
1.プライムレートとは何?
プライムレートとは「最も優遇された金利」のことで、銀行が企業などにお金を貸すときに使われる金利です。
特にプライムレートは、信用力の高い企業に対して適用される「最も低い貸出金利」を意味しています。
一般的に、日本銀行の政策金利によって変動し、景気が良くなると金利は上がり、景気が悪化すると金利が下がります。
このプライムレートには、「短期プライムレート(短プラ)」と「長期プライムレート(長プラ)」の2種類があります。
短プラは、1年以内の短期融資に適用される金利で、各銀行が短期金融市場の動向を参考にして決定します。
長プラは、1年以上の長期融資に適用される金利で、主に長期国債など債券市場の影響を受けやすく、短プラに比べて金利の変動が大きくなる傾向があります。
住宅ローンの金利も、この短プラ・長プラの動きと深く関係しています。短プラと長プラの違いをそれぞれ見てきましょう。
2.「短プラ」「長プラ」の違いは?
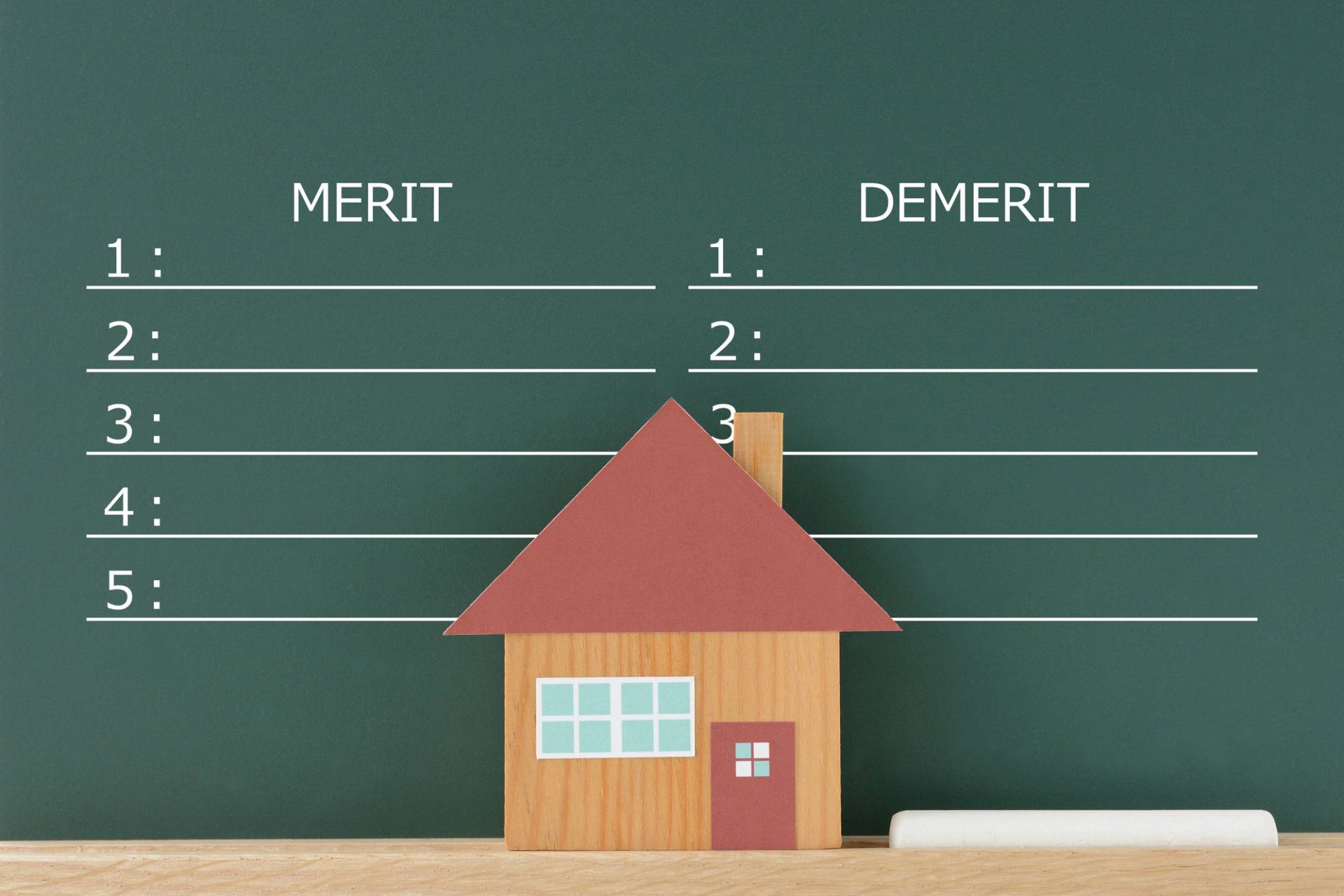
短プラと長プラの違いを理解してもらうために、ここでは、それぞれの概要とメリット・デメリットを解説します。
(1)短プラとは?
「短プラ」とは、「短期プライムレート」の略称で、銀行が優良企業に対して1年未満の短期融資を行う際の基準金利を指します。
この金利は、住宅ローンの変動金利型や、教育ローンなどの金利設定にも利用されており、家計とも深く関わる重要な指標です。
短プラは、金融機関が市場の短期金利(たとえば譲渡性預金=CDの金利など)を参考に独自に決定しており、通常は半年ごとに見直されます。
かつては、日本銀行の公定歩合に連動して決定されていましたが、1989年以降は、市中の金利動向を反映する形へと移行しました。
メリット
金利が比較的安定している
短期融資であるため、長期融資(=長プラ)に比べて金利の変動が少なく、一般に低めに設定される傾向があります。
金利水準が低い傾向にある
変動金利型ローンなどでは、低金利時代の恩恵を受けやすく、支払い負担を抑えられる可能性があります。
一般的に資金を貸出す際は、長期よりも短期の方がリスクが低いとされています。そのため、短プラの方が金利が低く変動が少ない傾向にあるのです。
デメリット
金利上昇時に返済額が増えるリスク
短プラが上がれば、変動金利型の住宅ローン金利も上昇し、毎月の利息の支払い額や返済額が増えることがあります。
金融機関ごとの「優遇幅」に差がある
実際に適用される金利は、「短プラ + 金融機関独自の上乗せ幅(または優遇幅)」で決まります。
この優遇幅は銀行によって異なるため、事前に比較・確認が重要です。
(2)長プラとは?
「長プラ」とは、「長期プライムレート」の略称で、銀行が1年以上の長期融資を行う際に用いる基準金利を指します。
この金利は、住宅ローンの固定金利型など、長期間にわたる資金の貸出しに広く使われています。
長プラは、長期の債券市場(特に長期国債の利回りなど)を参考にして決定されるのが特徴です。
そのため、金融政策や景気見通しの変化など、経済全体の動向に左右されやすく、金利が上下に大きく変動する傾向があります。
メリット
返済計画が立てやすい
長期プライムレートを基準金利とする固定金利型のローンでは、借入当初に金利が確定するため、毎月の返済額が一定となり、将来の資金計画が立てやすくなります。
金利上昇時の影響を受けにくい
金利が上昇しても、契約時に決まった金利がそのまま適用されるため、変動金利よりもリスクが抑えられます。
デメリット
短プラに比べて金利が高めに設定されやすい
長期間の貸出しは金融機関にとってリスクが大きいため、金利は短プラよりも高くなる傾向にあります。
金利が下がっても恩恵を受けにくい
固定金利で契約した場合、途中で金利が下がっても、原則として契約時の金利は変更されません。
3.「短プラ」「長プラ」が与える影響

短プラと長プラが与える影響を「経済」と「住宅ローン」の二つの視点で解説します。
(1)経済への影響
短期プライムレート(短プラ)や長期プライムレート(長プラ)は、経済全体にも少なからず影響を及ぼします。
一般的に金利が下がれば、企業や個人がお金を借りやすくなり、資金が市場に多く流通します。その結果、消費が活性化し、企業の業績が改善、物価が上昇するなど、景気を押し上げる効果が期待されます。
たとえば、金利の低下によって住宅ローンを組みやすくなれば、住宅着工件数が増え、建築業界や関連産業にも好影響をもたらします。これがいわゆる金利と景気の関係におけるセオリーとされています。
近年では、賃金と物価の上昇を受けて、日本銀行は2024年3月にマイナス金利政策の解除を決定しました。その後2024年7月と2025年1月に政策金利を引き上げる「利上げ」を発表しました。これによって住宅ローンの金利も上昇しています。
(2)住宅ローンへの影響
2025年5月現在、短期プライムレート(短プラ)は、主要行で年1.875%に引き上げられています。これによって変動金利型住宅ローンの店頭金利も同様に上昇傾向にあります。
一方、長期プライムレート(長プラ)は2016年7月に年0.9%まで下がりましたが、2025年5月現在は年2.05%に設定されています。 これは、長期固定金利型住宅ローンの金利にも影響を及ぼしており、全体的に金利上昇の局面に入っていることがうかがえます。
このような金利上昇の背景には、日本銀行によるマイナス金利政策の解除や、段階的な政策金利の引き上げがあります。 これにより、短プラや長プラが上昇し、住宅ローン金利にも影響を及ぼしています。
2025年5月現在、変動金利型住宅ローンの適用金利は年0.5%〜1.2%程度、全期間固定金利型は年1.9%〜3.8%程度となっており、過去の低金利水準と比較すると上昇傾向にあります。(※金利は2025年5月30日時点のもの)
今後、景気の動向や金融政策次第では、さらなる金利の変動が予想されます。 特に、長期にわたる住宅ローンを検討されている方は、将来的な金利上昇リスクを踏まえ、固定金利型の選択肢も視野に入れることが重要です。
4.まとめ・「短プラ」「長プラ」の違いについて
今回は「短プラと長プラの違い」をテーマに解説しました。
「短プラ」は変動金利に、「長プラ」は固定金利に影響がある指標です。
日本では長く、マイナス金利が導入されていたこともあり、金利変動型の住宅ローンを選択することが一般的なセオリーとされてきました。
住宅金融支援機構による住宅ローンの実態調査では、実に住宅ローン利用者の77%が変動金利型を選択しています。
とはいえ、全ての人に確実に変動金利が最適というわけではありません。金利変動型は金利が上昇すると、返済額が増えてしまうというデメリットもあります。
一方で固定金利型は、金利が一定で安定しているため返済額が予測しやすいというメリットがあります。将来の収支計画やライフプランニングによっては、固定金利型の方が良い場合もあるのです。
ご自身のライフプランを見つめ直すきっかけとして、住宅ローンの金利選びも大切なステップの一つです。将来の安心につながる判断のために、情報をもとにじっくり考えてみてください。

