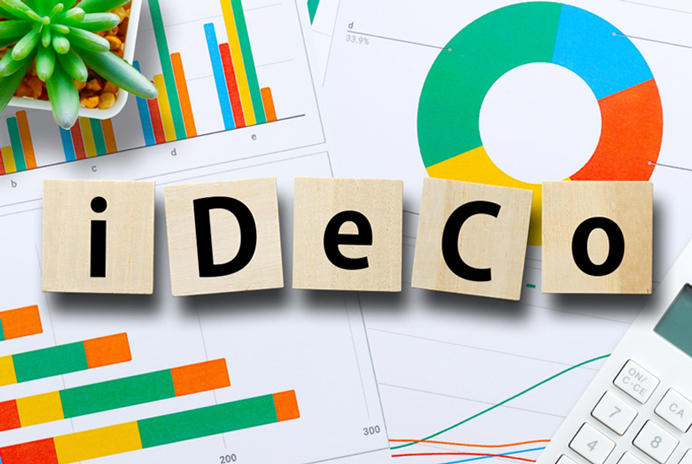
こんにちは、FPバンク編集部です。
「iDeCoを使うと節税できる」
このようなフレーズを聞いたことがありませんか。
しかし、節税といってもどの税金がどのくらい減るのかまで理解できている方は多くないでしょう。
本コラムでは「いつ」「どの税金が」「いくらぐらい」節税できるのか、年収別に例を示しながらお伝えします。
これからiDeCoを始めようと思っている方もすでに始めていらっしゃる方も、iDeCoの節税効果がどの程度のものなのか、他にはどのような節税方法があるのか、参考にしていただければ幸いです。
目次
1. iDeCoの節税効果とは?

iDeCoでは、掛金の拠出時・運用時・年金の受取時と3つのタイミングでそれぞれ節税効果を得られます。どのような効果があるのか確認していきましょう。
(1)拠出時
iDeCoでは、掛金の全額が所得控除の対象です。
たとえば月額23,000円を1年間拠出すると、年間で276,000円が所得控除となり、結果的に所得税と住民税が軽減されます。
たとえば所得税率が10%、住民税率が10%なら、節税額は年間で約55,200円です。会社員は年末調整、自営業者は確定申告で税金が還付されます。
なお収入によって税率が変わるため、節税効果の程度も収入によって異なります。
(2)運用時
iDeCoの口座内で発生した運用益はすべて非課税です。
投資信託なら売却益や配当、利息に対して通常20.315%の税金が課されますが、iDeCoではこれらすべてが非課税となります。
非課税という点ではNISAと似ていますが、NISAでは元本確保型の商品を選べません。
一方、iDeCoでは定期預金や元本確保型の保険の他、国内外の株式・債券で運用する投資信託も選べます。
ただ、元本確保型の商品はリスクが抑えられる代わりに期待できる利益も限定的です。投資信託を活用すれば、投資先を分散してある程度リスクを抑えながら、元本確保型よりも大きな利益を期待できます。
<関連記事>「わからないNISA」 を 「わかるNISA」に
(3)受取時
iDeCoで積み立てたお金の受け取り方には、①一時金として受け取る、②分割して年金で受け取る、③一時金受け取りと分割受け取りの併用の3パターンがあります。
各パターンで税金のかかり方が異なるため、それぞれ整理していきましょう。
① 一時金として受け取る
一時金で受け取る場合は「退職所得控除」が適用されます。退職所得控除とは働いた期間に応じて一括受け取りの退職金にかかる税金が優遇される制度です。
退職金から控除できる金額は下記のとおりです。
- 勤続年数が20年以下の場合:40万円×年数
- 勤続年数が20年超の場合:800万円+70万円×(勤続年数-20年)
ですから、23歳から60歳まで37年間勤務した場合は以下のとおりです。
800万円+70万円×(37年-20年)=1,990万円
つまり1,990万円までの退職金が税金の計算から外れます。
大卒から定年まで働いて、会社の退職金とiDeCoの一時金の合計が2,000万円程度なら、ほぼ税金がかかりません。
② 分割して年金で受け取る
iDeCoで積み立てたお金を分割して年金で受け取る際には雑所得に分類され、公的年金等の収入の合算額に応じて公的年金等の控除の対象となります。
公的年金等の収入の合計額が65歳未満は60万円まで、65歳以上の場合は110万円までは税金がかかりません。
③ 一時金受け取りと年金受け取りの併用
このパターンは①と②の組み合わせです。①②をご参照ください。
なお、一時金として受け取るか、年金形式で受け取るかは受け取り時に選択できます。加入時に決めておく必要はありませんので、マネープランに合わせて検討するとよいでしょう。
2. 【年収別】iDeCoの節税効果シミュレーション

さて、掛金の拠出時・運用時・受取時の節税効果は具体的にどれくらいになるのか、5パターンの年収別でシミュレーションしてみましょう。
シミュレーションの条件は下記のとおりです。
- 「年収」は手取りではなく額面年収を指す
- (1)~(4)においては配偶者・子どもなしを想定
- (5)では子どもなしを想定
- 毎月の掛金は23,000円
- 運用期間は30年
- 運用利回りは年率3%(複利)を想定
ここでの年収は「手取り」ではなく額面収入を指し、(1)~(4)においては配偶者・子どもなしを想定しています。
(1)年収350万円の場合
【拠出時】
所得税、住民税合わせて年間41,400円を節税できます。
【運用時】
節税額はおよそ100万円です。
30年間で積み立てた元金は828万円で、運用によって1,334万円に増えています。
1,334万円-828万円=506万円の利益に対して通常20%が課税されるため、本来の税額は100万円ほど。iDeCoでは運用益が非課税ですから、約100万円を節税できます。
【受取時】
一時金で受け取る場合は会社の退職金の金額、年金として受け取る場合は公的年金の金額によって、節税額は変動します。
ただし、いずれにしても退職所得控除、公的年金控除を適用できる点は上述のとおりです。
(2)年収500万円の場合
【拠出時】
所得税、住民税合わせて年間55,200円を節税できます。
【運用時】
節税額はおよそ100万円です。30年間で積み立てた元金は828万円で、運用によって1,334万円に増えています。
1,334万円-828万円=506万円の利益に対して通常20%が課税されるため、本来の税額は100万円ほど。iDeCoでは運用益が非課税ですから、約100万円を節税できます。
【受取時】
一時金で受け取る場合は会社の退職金の金額、年金として受け取る場合は公的年金の金額によって、節税額は変動します。
ただし、いずれにしても退職所得控除、公的年金控除を適用できる点は上述のとおりです。
(3)年収800万円の場合
【拠出時】
所得税、住民税合わせて年間82,800円を節税できます。
【運用時】
節税額はおよそ100万円です。30年間で積み立てた元金は828万円で、運用によって1,334万円に増えています。
1,334万円-828万円=506万円の利益に対して通常20%が課税されるため、本来の税額は100万円ほど。iDeCoでは運用益が非課税ですから、約100万円を節税できます。
【受取時】
一時金で受け取る場合は会社の退職金の金額、年金として受け取る場合は公的年金の金額によって、節税額は変動します。
ただし、いずれにしても退職所得控除、公的年金控除を適用できる点は上述のとおりです。
(4)年収1000万円の場合
【拠出時】
所得税、住民税合わせて年間82,800円を節税できます。
【運用時】
節税額はおよそ100万円です。30年間で積み立てた元金は828万円で、運用によって1,334万円に増えています。
1,334万円-828万円=506万円の利益に対して通常20%が課税されるため、本来の税額は100万円ほど。iDeCoでは運用益が非課税ですから、約100万円を節税できます。
【受取時】
一時金で受け取る場合は会社の退職金の金額、年金として受け取る場合は公的年金の金額によって、節税額は変動します。
ただし、いずれにしても退職所得控除、公的年金控除を適用できる点は上述のとおりです。
(5)専業主婦(主夫)の場合
【拠出時】
専業主婦の方は所得税の計算のもととなる収入がありませんから、拠出時の税制優遇もありません。
【運用時】
節税額はおよそ100万円です。30年間で積み立てた元金は828万円で、運用によって1,334万円に増えています。
1,334万円-828万円=506万円の利益に対して通常20%が課税されるため、本来の税額は100万円ほど。iDeCoでは運用益が非課税ですから、約100万円を節税できます。
【受取時】
会社に勤めておらず、他に退職金のない専業主婦(主夫)は退職所得控除をiDeCoの一時金にまるまる適用できます。専業主婦(主夫)でも、iDeCoで積み立てたお金を一時金として受け取る場合は「退職所得」として扱うためです。
退職所得控除の算出にはiDeCoの加入期間を使います。この場合は30年ですから、800万円+70万円×(30年-20年)=1,500万円です。
iDeCoの資産1,334万円は退職所得控除の枠内に収まるため課税所得は0円となり、所得税は発生しません。
年金受け取りを選んだ場合は公的年金等控除ももちろん適用でき、いくつから受け取るか、何年間かけて受け取るかによって控除額が変わります。
3. そもそもiDeCoとは?

iDeCoは個人型確定拠出年金の略で、国民年金や厚生年金とは別に自分で資産を形成していきます。
iDeCoに加入する個人が毎月一定金額を積み立て(掛金の拠出)、預金や投資信託など金融機関が用意している商品の中からひとつまたは複数を選んで運用します。
積み立てたお金は60歳以降に一時金もしくは年金形式で受け取れます。
国や会社からの年金以外に自分で老後のお金を積み立てて、自分で運用していく点がiDeCoの特徴です。
掛金は1,000円単位、最低5,000円から積み立てられます。積み立ての上限金額は職業(国民年金の加入者区分)によって異なります。
iDeCoを利用できる人の区分と、積み立ての上限金額を整理していきましょう。
(1)利用できる人
iDeCoには原則として20歳〜65歳未満のすべての方が加入できます。国民年金の加入区分によって積み立てられる限度額が変わるため、まずはご自身の加入区分を確認しましょう。
●国民年金の第1号被保険者:20歳~60歳未満の、会社員や公務員でない人
○自営業者、フリーランスなど
●国民年金の第2号被保険者:厚生年金の被保険者
○会社員や公務員
●国民年金の第3号被保険者:厚生年金の被保険者に扶養されている20歳~60歳未満の配偶者
○専業主婦(主夫)など
●国民年金の任意加入被保険者:国民年金に任意で加入した人
○60歳以上60歳未満で、国民年金の保険料の納付済期間が480ヵ月に達していない人など
(2)積み立てられる金額
職業(公的年金の加入区分)ごとに積み立てられる金額は下記のとおりです。
●自営業者・任意加入被保険者:月額68,000円
●会社員
○企業年金がない場合:月額23,000円
○企業型DCやDBに加入している場合:月額20,000円
●公務員:月額20,000円
●専業主婦(主夫):月額23,000円
なお企業型DCやDBに加入している会社員、公務員の上限20,000円は下記の範囲内に収まったうえでの金額です。
●月額55,000円-(各月の企業型DCの事業主掛金額+DB等の他制度掛金相当額)
4. iDeCoの注意点

先述したとおり掛金の拠出時・運用時・受取時の節税効果が大きなメリットであるiDeCoですが、利用にあたって注意点もあります。とくに注意したい3点を押さえていきましょう。
(1)60歳まで引き出せない
年金という名のとおり、積み立てたお金の受け取りは老後に入ってからです。60歳になるまでは、原則として積立中のお金を引き出せません。年金=老後の資産のための制度ですから、ある意味仕方がないともいえます。
老後の年金は貯まっているのに今使えるお金が手元にない!といった事態に陥らないよう、計画を立てて利用しましょう。途中の引き出しはできませんが、拠出額は変更できます。お金が必要な時期や、産休・育休中などで収入が下がる時期などは毎月の掛金を減額して調整していくとよいでしょう。
たとえ毎月の掛金が最低額の5,000円だったとしても、30年積み立てつづければ元本だけで180万円になります。もし年率3%で運用できたら、30年後には元本と運用益を合わせて約290万円になります。
毎月の掛金が少額でも長い時間をかければ複利の効果でそれなりに大きな金額となる可能性が高いため、多額の積み立ても大切ですが長期間の積み立て=早く始めることも大切です。
(2)値下がりのリスクがある
iDeCoでは預金や投資信託など金融機関が用意した金融商品の中からご自身の好きなものを選んで運用していきます。
先ほども少しふれましたが、預金をはじめとする元本確保型の商品は、元本保証=低リスクの代わりに元本がほとんど増えません。
一方、投資信託は元本保証ではない=リスクのある金融商品です。株式市場や世界情勢の影響で価格が変動しますから、当然値下がりもありうるでしょう。値動き(リスク)の大きさは投資信託の種類によって異なります。
もし値下がりしたとしても、投資信託を売却さえしなければ損失を「抱えている」状態に留まり、実際の損失はまだ出ていません。ここではくわしい解説を割愛しますが、積立投資を20年、30年と続けると最終的にはプラスに落ち着く可能性が高いとのデータもあります。
必要以上にリスクを恐れず、掛金の一部でもリスク性商品の利用をおすすめします。
(3)手数料がかかる
iDeCoでは新規加入時・移換時・運用期間中に手数料が発生します。新規加入時と移換時の手数料はどの金融機関を利用しても一律で2,829円です。一方で運用期間中の口座管理料は金融機関によって異なります。月々数百円程度ですが、数十年ともなると大きな差になります。
先ほどリスク性商品の利用をおすすめした別の理由は、口座管理料をカバーする目的もあります。元本確保性商品のみで運用すると、運用益を手数料が上回り、せっかく数十年積み立ててもお金が増えないかもしれません。
iDeCoで利用する金融機関を選ぶ際は必ず手数料を比較し、繰り返しになりますが元本確保商品だけでなく投資信託などリスクのある商品も採用しましょう。
<関連記事>FP相談で効果を最大にする6つのポイント
5. iDeCo以外の節税方法は?

iDeCo以外にも所得税や住民税を軽減する方法は多くあります。ここではそのうちごく基本的なものを3つ紹介します。
(1)住宅ローン控除
家の購入を検討している方にとって魅力的な節税方法である「住宅ローン控除」。
年間最大315,000円が税額控除されるため、一個人ができる節税策としては間違いなく上位に食い込んでくるでしょう。
ただし住宅ローン控除は改正が頻繁で、適用条件や控除額がよく変更されます。マイホームを建てる・購入する前に必ず内容を確認してください。
(2)生命保険料控除
保険料控除は全部で3種類あり、内容は下記のとおりです。
- 一般生命保険料控除
- 介護医療生命保険料控除
- 個人年金保険料控除
1年間に支払った保険料によって所得からの控除額が決まっており、3種類すべて下記の計算式で求めます。
【年間の支払保険料と所得控除の額】
- 20,000円以下:支払った保険料の全額
- 20,000円超 40,000円以下:支払った保険料×0.5+10,000円
- 40,000円超 80,000円以下:支払った保険料×0.25+20,000円
- 80,000円超:一律40,000円
たとえば一般生命保険料、介護医療生命保険料、個人年金保険料をいずれも10万円ずつ支払った場合は、合計120,000円が所得から控除されます。
生命保険本来の目的は「保障」ですから、控除を受けるための生命保険加入は目的から外れてしまう点には注意が必要ですが、必要な保障を確保したうえ控除で税金が戻ってくると嬉しいですよね。
(3)小規模企業共済
小規模企業共済は個人事業主を対象とする退職金のような制度です。
月々の掛金は1,000円から70,000円の範囲内で、全額を所得控除できます。年間では840,000円、また1年以内に前払いした掛金も同様に控除できるため、控除額は最大168万円となります
<関連記事>贈与税の非課税枠を活用すると数百万円得する?
まとめ
iDeCoは老後のお金を貯めつつ運用によってさらに殖やせる非常にメリットの大きい制度です。
拠出時・運用時・受取時には税制の優遇があるため魅力的な節税手段でもあります。
一方で運用失敗による資産減少のおそれがある点、60歳になるまでは引き出せないため流動性を失う点には注意が必要です。
iDeCoに加入する前に老後の生活で必要な資金を確認し、そのうちどのくらいをiDeCoで貯めていくのか、どのくらいリスク性の金融商品を選ぶのか考えておきましょう。

