
日経平均株価、という言葉は新聞やニュースで見聞きするけれど、内容はよく分からない、人に説明できない。という人は意外と多いものです。
この記事では「日経平均株価とは何か、上がるとどうなるのか」を知りたい方に向けて日経平均株価の変動が私たちの身の回りにどのような影響を与えるのかを解説していきます。
まず結論から言えば、日経平均株価とは、日本経済新聞社が東京証券取引所のプライム市場に上場している約2,000銘柄から225社を抜き出して、その株価をもとに算出している指数のことです。選出する際は、活発に売買されていることや業種の偏りが出ないようにするといった要因が考慮されています。
日経平均株価以外の株価指標として、日本のTOPIX、米国のNASDAQ、S&P500といった指標があります。
それでは日経平均株価とは何か、銘柄の内訳はどうなっているのかを、詳しく説明していきます。
目次
1.日経平均株価とは?

まずは、日経平均株価とは何かを詳しく解説します。
(1)日本の景気を表す重要な指標
毎日の経済ニュースの最後には必ず「今日の日経平均株価はいくらで、ドル円の為替はいくら」という情報が提供されます。また、日経平均株価の価格が大きく動くとそれが経済情報のトップ―ニュースとして扱われます。
日経平均株価は、東京証券取引所(東証)の一部に上場している2,000社前後の中から日本経済新聞社が日本を代表する企業として225社を指定し、その株価の平均価格を指数化して発表している指標です。いわば「日本の景気の変化」を代弁しており、景気判断の指標として重要なものです。
では、その225社とはどのように選ばれているのでしょうか?
(2)日本企業の代表225社の内訳とは
日本を代表する225社の内訳ですが、東証に上場している企業はそれぞれの業種ごとにセクターと呼ばれる分類がなされています。現在のその業種は35業種。上場している企業には「企業コード」という4ケタの数字が指定されており(例えば、トヨタ自動車なら7203)その先頭2桁の数字がおおむねその業種を表しています。セクターの分類には金融・保険業、建設業、商業、サービス業などがあり、その業種における経済的寄与度の高い企業が選ばれています。
例えば、自動車セクターでいえば、トヨタ、日産自、ホンダ、いすゞ、マツダ、日野自、三菱自、SUBARU、スズキ、ヤマハ発の10社が指定されています。いずれの会社もみんなが知っている一流大企業です。
また、対象となっている225社は企業業績などにより定期的に見直しも行われていて、銘柄が入れ替わったりすることもしばしばあります。
(3)日本平均株価に影響を与える企業とは
日経平均が最高値を付けたのは1985年末(大納会)の3万8,915円で、日本がバブル経済の頃でした。ここ30年間での最安値はリーマンショック時の2008年10月の6,995円。日経平均株価は世界情勢や地政学リスクにも大きく影響を受けます。近年では東日本大震災、チャイナショック、イギリスのEU脱退決定(ブリグジット)、トランプ大統領の当選などによって日経平均株価が1日で1,000円以上も動く日もありました。
また、日経平均株価の決定に大きく影響を与える企業があります。その企業のことを「日経平均株価に寄与度の高い銘柄」、「値がさ株」と言われることがあります。現在、3つの企業が寄与度の高い銘柄として有名です。ファーストリテイリング、キーエンス、SMCです。これらの企業の株価はいずれも高値のため、経済ニュースでもよく取り上げられています。
では、この日経平均株価は私たちの生活にどのような影響を与えるのでしょうか。
「資産運用」コラム一覧
2.日経平均株価が上がるとどうなる?

ここからは一般的に、日経平均株価が上がるとどうなるのかを解説します。
(1)日本経済への影響
株式市場は景気と密接に関連しています。
日経平均株価の変動を見ることで、景気がどのようになっているかを掴むことができます。
景気が良くなれば、企業の業績はさらに良くなることが予想されますから、株式の買い手が増えよりいっそう株価が上昇するでしょう。
とはいえ、日経平均株価と実際の景気の良し悪しのタイミングは完全に一致しているわけではありません。
(2)企業への影響
景気が良くなり株価が上昇すると、企業にも恩恵があります。
一般的に株価が上昇する要因は、企業の「業績」です。業績が良い企業は、将来的な成長も期待できるので株価が上昇する傾向にあります。
企業の業績が上がると、従業員の給料が上がったり、配当金が増えたりするので個人への恩恵も増えるでしょう。
(3)生活への影響
日経平均株価が上昇し景気が良くなると、個人消費者の消費意欲が高まる傾向にあります。一般消費者が企業のサービスや商品をたくさん購入することで、さらに企業の収益が増え、従業員や投資家へ還元される好循環が続きます。
3.日経平均株価が上がるデメリットはある?
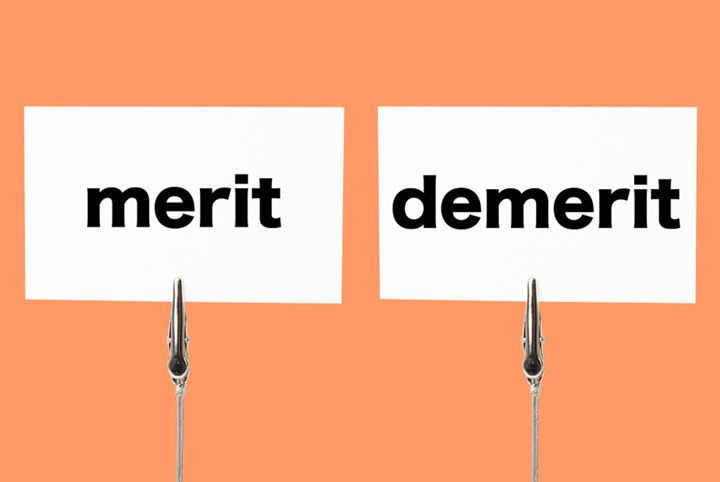
日経平均株価が上昇するデメリットは特にありません。
しかし「なぜ日経平均株価が上昇しているか」という原因には、メリットもデメリットも生じるので解説します。
例えば2024年現在、米国の景気が良いことから日本との間に金利差がうまれ、円安が進みました。金利の高い国の通貨は買われ、反対に金利の低い国の通貨は売られます。米ドルが買われ、日本円が売られたことで円安が進行し、一時は160円をつけていました。
円安は、輸出企業やインバウンド関連企業にはメリットになります。
円安になれば輸出企業の価格競争力が高まり収益が増加することが予想されるため、日本を代表するような大型株を中心に海外投資家から資金が流入し株価が上昇しました。
一方で、こうした円安は輸入企業にとってはデメリットになります。円安になると輸入品の価格が上がるため、電気やガスの燃料を輸入に頼っている日本では原料高による値上げ、といった形で一般消費者にも影響がでる可能性があります。
このように、日経平均株価の上昇自体はデメリットにはなりません。しかし「なぜ」上昇したのか、という原因にはメリットとデメリットがあるので覚えておくといいでしょう。。
4.まとめ
今回は「日経平均株価が上がるとどうなるのか?」をテーマに解説しました。
日経平均株価は日本に上場している企業の中でも、我が国を代表する大企業によって構成される株価指標です。他に、上場している企業全部で構成されるTOPIXもあります。
日経平均株価が上昇することで、景気がよくなり企業の収益が増加し、従業員や投資家といった一般消費者に恩恵があります。
とはいえ、重要なのは「なぜ」日経平均株価が上昇しているかです。円安・円高を理由としているのか、金利の上下が理由なのかで、それぞれメリットやデメリットが生じてくるので覚えておきましょう。
特に景気の良さを実感できないのに日経平均株価が上昇すると「バブルなのではないか?」と不安を感じてしまう人もいらっしゃるかもしれません。
最近の日経平均株価の上昇は、米国と日本との金利差による円安進行および、中国の景気低迷により投資先が日本に向かったことによる資金流入が要因の1つと言われています。
1989年バブル当時の、株価の割安・割高を示す「PER」という指標は62.58倍を付けていました。現在の指標は16.47倍、平均値は15倍程度ですから異常な数値ではありません。
資産運用の判断を間違えないためにも、「なぜ」日経平均株価が変動しているのかまでニュースや新聞で調べてみることをおすすめします。
調べたうえで、理解が難しい方や日経平均の動きだけでなく、経済の大きな流れが私たちの生活にどのように影響するのか不安に感じる人。
こうした外部要因を、自身の叶えたい未来に向けてどのように捉えるべきなのか分からない人。
こうしたお悩みがある人は、ぜひお金の専門家にご相談ください。
自分事に置き換えて一緒に整理し、多角的な視点でアドバイスできるプロが対応いたします。

